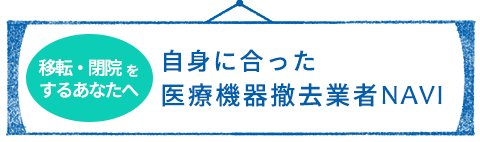保管義務のある書類の保管
閉院をしても保管しなくてはいけない書類がある?
医院を閉院するにあたって、個人情報が記載されているカルテの法的な保存期間や医療事件などに関する損害賠償請求権との兼ね合いなどを含めて説明します。管理責任や処分方法など、正しく理解しておかないと後日トラブルの原因となるリスクがあるので注意が必要です。
カルテの管理責任は
だれにある?
医院ではカルテを5年間保存することが法律で義務付けられていますが、その管理責任者は誰なのか、まずは医師法第24条第2項を引用してみましょう。
「病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間(法定保存期間)これを保存しなければならない」
この表記からすると、「勤務医の診療カルテの管理責任は管理者」にあり、「それ以外の診療カルテは医師に管理責任」があると理解できます。では、管理者は誰かというと、医療法第10条で「開設者の任命を受けた医師」と定義されています。
従って、個人経営の医院だと院長がカルテの管理責任者といえるでしょう。
状況によって変わる閉院時のカルテの管理責任
次に、医院が閉院する場合、カルテの管理責任者は誰になるのか、3つのケースに分けて説明します。
継承の場合
閉院する医院の事業を継承する医療機関が決まっている場合、カルテの管理責任も継承する医療機関に移ります。事業継承が完了すれば、閉院する医院側には管理責任がなくなります。
また、カルテの継承にあたって、患者さん一人一人の同意を得る必要はありません。個人情報保護法でも事業継承に伴うデータ提供が認められているからです。患者さん側の立場に立つと釈然としない面もあるので、正しく通知する方が無難ともいえます。
継承なしの閉院の場合
事業継承せずに閉院する場合はその時点の管理責任者=院長が、カルテを5年間保管しなければなりません。
一方、閉院したからといって医療事件やカルテ開示請求に関する患者さんの損害賠償請求権がなくなるわけではなく、10年という期間はカルテも保管するのが賢明。合わせて、医師賠償責任保険をチェックして、閉院後も保険適用が可能かどうか、特約の有無を把握しておくといいでしょう。
管理者死亡による閉院の場合
管理責任者である院長が亡くなって閉院する場合は、カルテの管理責任がなくなるので、遺族に管理責任が生じることはありません。その際、カルテの管理は厚生労働省の通達では「行政機関での保存が適当」となっているものの、実態は遺族と自治体が協議して決めるケースが多いようです。
なお、患者さんの損害賠償請求権が10年なのは同じで、カルテの管理責任とは別に、損害賠償義務は相続人に継承されます。それを加味すると、相続する人がカルテも10年は保管しておく方がいいともいえます。
保存期間経過後に
医院内を整理するなら、
トータルサポートの
業者に依頼を。
カルテの保存期間を過ぎたら、個人情報であるカルテはきちんと廃棄しましょう。電子カルテと紙カルテ両方とも、焼却や粉砕などの方法で処分します。
こうした個人情報の処分では、作業完了の証明書を発行してもらうところまでが管理責任です。依頼するのは情報セキュリティ認証ISO27001を取得している機密文書処理業者がよいでしょう。加えて、カルテの処分と医院内の整理全般と合わせてトータルサポートしてくれる専門業者だと、なお安心です。
このページを見ている方に、おすすめの他ページ
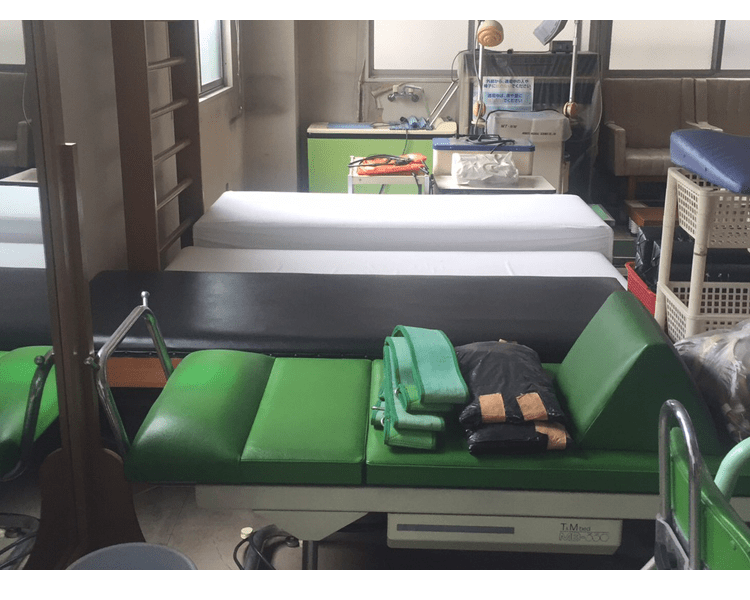
https://takemedical.net/
医院の数だけ、最適な撤去方法は変わる
医療機器の撤去は、病院それぞれに固有の事情があり、柔軟な対応ができる業者を選びたいと思うことでしょう。
ここでは、医療機器専門の撤去業者がHP上に掲載している撤去事例をまとめて紹介していきます。
事例とおすすめの撤去業者
当サイトでは医療機器撤去の専門業者を調べて、依頼事例ではそれぞれの医院の状況に合わせたケースをピックアップ。事例ごとにまとめているので、そちらも参考にご覧ください。